
監督 ルイス・オルテガ
Amazonプライムで字幕版を視聴。114分。
あらすじ:1971年、ブエノスアイレス。何不自由ない生活を送る17歳の美少年カルリートスだったが、遊びを楽しむように犯罪に手を染め、ほとんど罪の意識を感じることもなかった。やがて彼は、転校先で野性的な魅力に溢れたラモンと出会い意気投合し、2人でコンビを組んでさらなる罪を重ねていく。
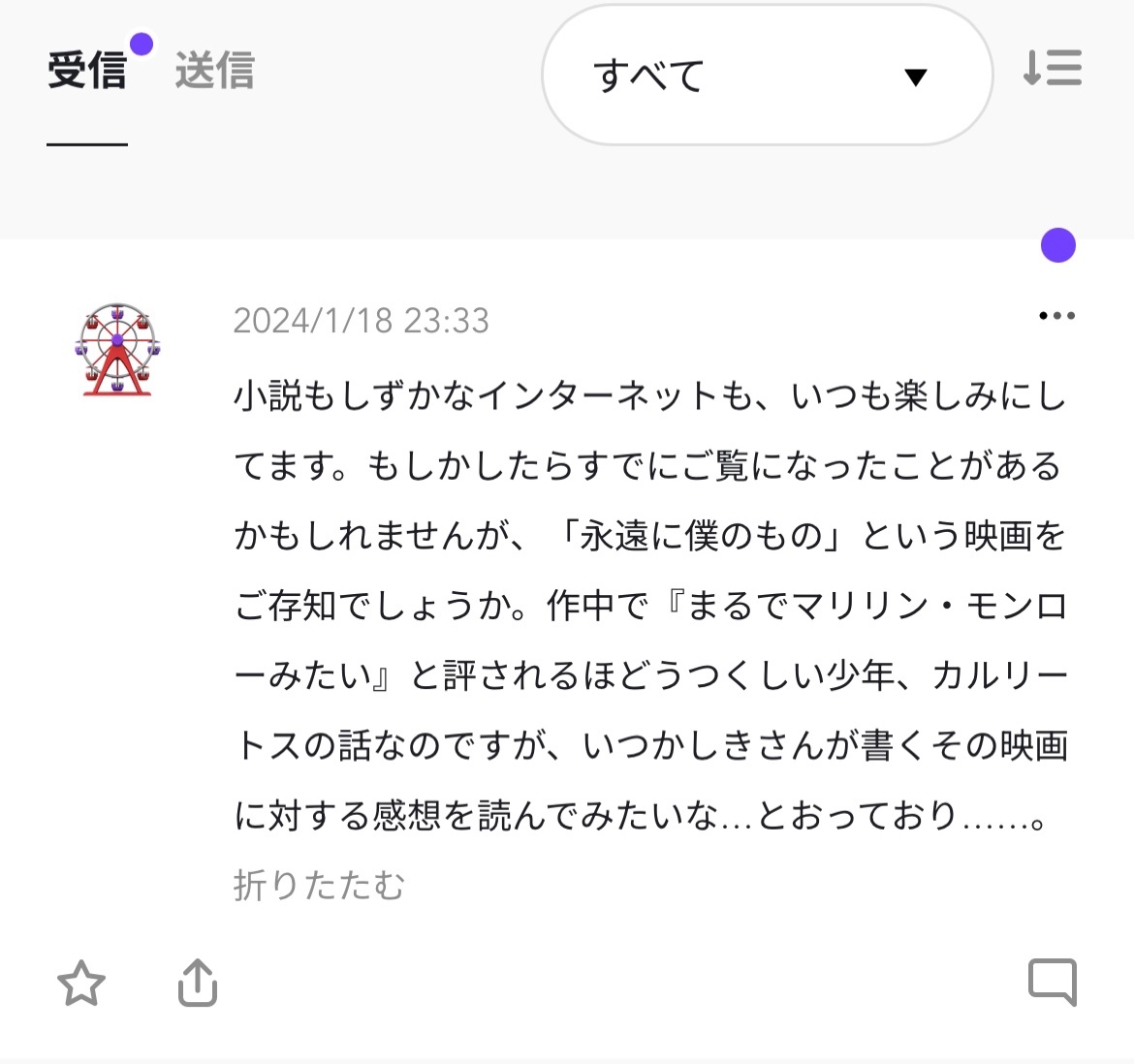
wave boxにておすすめしていただいたので観ることに。こういった形でおすすめの映画を教えていただけるのはとてもありがたいことだしとてもうれしい。ひとがひとにおすすめしたい映画というのは、それだけで相応の信頼と魅力を持つ。
さて、Amazonプライムに作品があるのかどうか検索しようとした際のサジェストに「実話」と出てきたのでわたしはその時点で震えたものだった。元になる実話が根に坐す映画はどんなものでも恐ろしいので身構えてしまう。そこに、映画に昇華してしまえるだけの凄絶な何かがあると相場が決まっているからだ。(わたしがホラー映画の「呪詛」を見ることができていないのは、かの作品が実在の要素を随所に組み込んだものであると知ったからだ。呪いは縁から伝うと信じているので、見たら呪われるかもしれない…と思ってしまう。つくづく、ホラー映画の鑑賞に向いていない。)どんなに辛い映画でも、怖い映画でも、悲しい映画でも、フィクションであるというのはある種救いである。観賞中の逃げ道であるともいえる。それが無いのは、それなりに覚悟をしなければいけない。多少のフィクションが混ぜられているとはいえ現実の人間が起こした、現実で起きた出来事なのだと認識する覚悟が要る。
「永遠に僕のもの」は1月23日に鑑賞した。この感想を書いているのは翌日の24日なのだが、今までの鑑賞録と異なり1日開けたのには訳がある。それはカルリーストもとい、カルロス・エドゥアルド・ロブレド・プッチが現実で起こした事件の詳細について調べ──調べていくさなか、カルリーストが逮捕された日がわたしの誕生日と同じで妙な運命のようなものを感じてしまった──端的に彼のことを知ることができるWikipediaを読んでから感想を書こうと思ったからだ。白状すると、彼について書かれているWikipediaが英語版のものしかなくて困った。訳すのにかなり時間がかかった。英語が読めたならその日の夜にこの鑑賞録が書けていた。英語の勉強を……しなければ……。
映画を観終えた最初の感想としては、カルリーストの持つ妖艶な色香を放つ美貌とそんな彼に内包された残虐性、そのギャップと起こした犯罪の数々が耽美的な映画の中に落とし込まれて多くの人の目を惹く価値を持つエンターテイメントと化している現実に、どこか皮肉さえ感じた、というものだった。犯罪者の心理にひとびとが興味を覚えるのはある意味必然だが、カルリーストの場合はどこか違う。そういった心や内面でなく、「美少年」が「多くの犯罪を犯した」という事実にばかり興味を持たされる点が、ひとの心理を上手く突いているように思えた。だって、相反する絶妙な組み合わせだ。
観終えた側の人間になってしまったからこそ、そしてわたし自身小説を書くことが好きな人間だからこそ、彼に歴史的犯罪者としての魅力を見出してしまう気持ちはわかる。ここまで突き詰められると、彼についての作品を作りたくなるのも無理はない。犯罪者をテーマにした創作物はこの世にありふれているし、わたしだって書くことがある。 ただ、然し、と考えさせられ部分もある。この作品が現実に起きた事件を基にしているからこそ思考する。もしもカルリーストが美少年でない醜い人間であったなら? 生来の犯罪者は醜い容姿を持った人間だという「ロンブローゾの理論」が当時信じられていなかったら? そしたらきっと、同じ犯罪の内容でもこのような映画には至らなかったろう。ひとびとの目をこんなにも惹かなかっただろう、とも思う。稀代の美少年殺人鬼であるがゆえに! だからこそ、映画の趣旨とはややずれた考えかもしれないけれども「うつくしいとは?」と深く考えさせられもした。
うつくしいだけで、その人生が、犯された犯罪が、より劇的でドラマチックに観えてしまうトリックにかけられつつ、わたしは「永遠に僕のもの」を見た。
あとその……これは余談なのだがわたしはもともと海外の人間の名前を覚えるのが苦手で……カルリーストの名をいつまで経ってもちゃんと覚えられなかった。ラモンは一発だったのに。カルロ……カロ……カルロ―トス……カルリートス……? だったっけ……などと間違え続けていた。猛省である。
印象に残ったシーンは多々あった。冒頭のポップなダンスシーンは言わずもがなで、キービジュアルに設定されている入浴シーンのほか、ラモンの母にくちびるをゆっくりと撫でられるシーン、宝石を耳に着けカルリーストがラモンに「マリリンモンローみたい」と言われる件のシーンなど、そのそれぞれは観客にカルリーストを意図的に見蕩れさせるような──時に彼を無垢な少年のように、時に婀娜っぽい表情をちらと見せるおとなのように──画角でおさめられており、やるな……。と思わされた。挑んでもないのに負かされたような気分だ。カルリーストは、顔のアップがとにかく多い。特に、垂れた目と色づいたくちびるに目がゆくようカメラが捉える位置も計算されている。カルリーストを演じるロレンソ・フェロの表現力といったら……。こんなふうに映されてしまっては、どうしたって好きになってしまう。現実の彼もきっとこうだったのだろうと想像させられてしまう。よくできた仕組みだ。ついでに、カルリーストの服がおしゃれでかわいいなと思っていたら、映画的表現というわけでなく実際のカルロス・エドゥアルド・ロブレド・プッチもおしゃれだったらしいということなので感心させられた。原作に忠実ということでその再現率は大変好ましい。実在の人物を基にしているだけはある。
ラモンとカルリーストの距離感もまた絶妙だった。同性愛的表現は然程濃厚でなかったけれども匂わせ方がさりげなく、それでいて互いが線の内側で境界を越えてしまうか越えまいかと足踏みしている雰囲気もあった。テレビに出たラモンに恋人の有無を問う場面を入れたのも良い。というかカルリーストはもちろん、ラモンもとても格好良くて目が奪われるばかりだった。彼らが間反対の美貌を持つことそれ自体が、相棒という関係性と何より絵面に合っている。あの伏し目がちな目元、よかったな……。彼らの終わりがトンネル内の交通事故で迎えられたのもカルリーストの意図を感じさせられるようだった。トンネルを超えた先の光(ラモンが憧れていたテレビなどのスポットライトが当たる場所)には出さない、というような想いだ。
カルリーストの犯罪に対する躊躇いのなさを目の当りにする都度、「もっとみんな自由に生きたらいい」と映画冒頭で出てきた言葉が思い出された。カルリーストの名前もどうやら自由に関するもので、このテーマは映画中にも何度か出てくる。これは個人的な解釈に過ぎないが、カルリーストが極めて自らに素直に、自由に才能を発揮して生きる結果伴うのが窃盗であり、殺人であるだけなのだ。ひとに銃を向けて尚、発狂も悔恨もなければただただ過ぎゆく現実に適応するカルリーストのあどけなさの残る顔が映される都度、ああ……と観客は察せられてしまう。善良な両親の元に生まれようと、その生来の気質を変えることはむつかしい。そういう星の元に生まれて、そうした運命を歩んでゆくほかないと受け入れるしかない。カルリーストを案ずる両親の姿には、彼彼女らが善良であることを知ら締められる都度心が痛んだ。然し彼らにはどうしようもない。盗んできたお金は庭に埋めるしかなく、やわらかな笑顔を見せる息子を前に何も言えなくなる。その無力感が、艶めかしくあやうい映画から漂う痛々しさでもあった。
カルリーストの立ち振る舞いは終始つかみどころがない。顔立ちもあどけなく、悪意がにじんだようには見えないことが多い。硝煙ののぼる向こうに見えるかんばせは悪など知らぬ天使のようだった。それがこの映画のミソなのだとエンドロールを眺めながら思った。つくづく人間の容姿は厄介だ。うつくしくあればあるだけ!
カルロス・エドゥアルド・ロブレド・プッチは今でも刑務所で生きており、51年以上の刑務所生活を送っているらしかった。この年数は南米で最も長い。服役中の彼が安楽死や致死注射による処刑を求め、死刑執行を要求している記録から、終身刑という刑の重さを改めて知る。
よい映画を観させてもらった。おすすめしていただき、ありがとうございました。