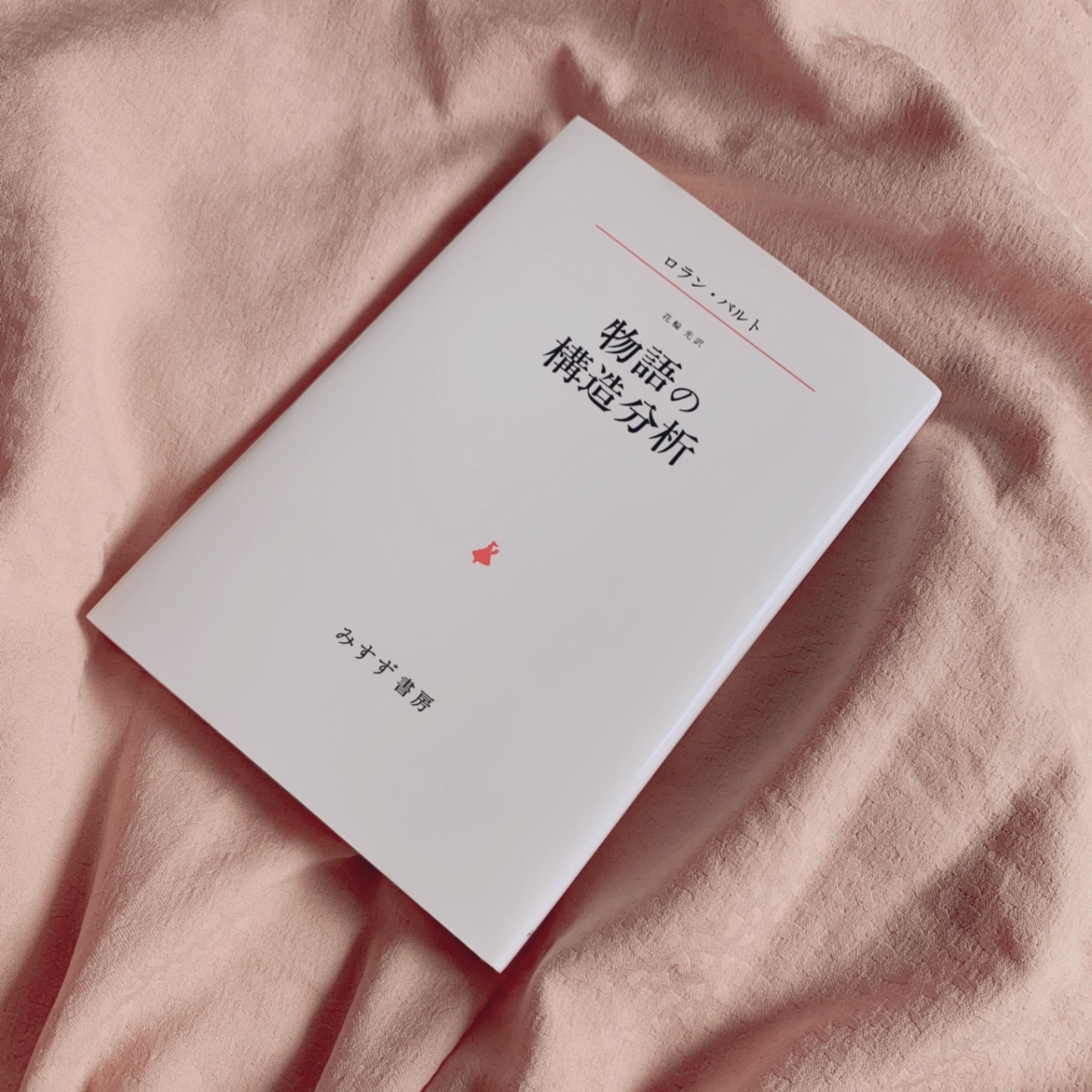
最近、モアメド・ムブガル・サール (著), 野崎 歓 (訳)『人類の深奥に秘められた記憶』を読んでいる。
その本の重要なモチーフのひとつにロラン・バルトがあり、それならばと『物語の構造分析』も読んだ。理解できたわけではないが(過去に何度も挫折した本だ)、重要だと思う箇所を以下に抜き出す。
ロラン・バルト (著), 花輪 光 (訳)『物語の構造分析』所収「作者の死」より引用
テクストとは、無数にある文化の中心からやって来た引用の織物である
これは作中でエリマンという小説家が主張していることに通じる。エリマンは「アフリカの作家」としての呪縛から逃れるために、「作者の死」を体現しようとしたのだと思う。
…この多元性が収斂する場がある。その場とは、これまで述べてきたように、作者ではなく、読者である。読者とは、あるエクリチュールを構成するあらゆる引用が、一つも失われることなく記入される空間にほかならない。あるテクストの統一性は、テクストの起源ではなく、テクストの宛て先にある。しかし、この宛て先は、もはや個人的なものではありえない。読者とは、歴史も、伝記も、心理ももたない人間である。彼はただ、書かれたものを構成している痕跡のすべてを、同じ一つの場に集めておく、あの誰かにすきない。だからこそ、偽善的にも読者の権利の擁護者を自称するヒューマニズムの名において、新しいエクリチュールを断罪しようとすることは、ばかげているのだ。
作品と作者を切り分けることを望んだエリマンを、しかし、ファイ(メインの語り手)は結局むすびつける。
『人類の深奥に秘められた記憶』456ページ、「…『人でなしの迷宮』の物語と著者の人生の関係について最後に問うた。その一片なりとも知ったいま、おまえは著者の人生をその本とどのように結びつけるのか?……」最初に読んだとき、なぜこの文を書いたのだろうと思った。
皮肉だろうか? 私がバルトを理解できていないから、この結末の意味がわからないのだろうか? バルト以外に読み込めていないさらに大きなモチーフがあるのか?
訳者解説に「自分は歴史を明晰に見つめながら別の何かを生み出したい、過去の糾弾や告発を超えた作品を書きたいとサールはインタビューで語っている」とあり、これが答えな気もする。読者への挑戦。
エリマンがフランス人のやり方で「アフリカ人作家」の呪縛に挑み、敗れ、それを見つめるファイもまた、白人のものの見方をしている。そんな物語を作ったセネガル生まれの作者と、その作品を結びつけるかの問いを突きつけられている読者の私。
帯の惹句に「なぜ人間は、作家は、「書く」のか」とあり、小説のなかでもそれは大切なモチーフとして機能しているのだけど、ことエリマンに関しては「どう「読む」のか」という問いがメインな気がする。