久しぶりだからなるべく面白いものを書かなければすまないという気がいくらかある。
それに自分の健康状態やらその他の事情に対して寛容の精神に充みちた取り扱い方をしてくれた社友の好意だの、また自分の書くものを毎日日課のようにして読んでくれる読者の好意だのに、酬いなくてはすまないという心持がだいぶつけ加わって来る。で、どうかして旨いものができるようにと念じている。
けれどもただ念力だけでは作物のできばえを左右する訳にはどうしたって行きっこない、いくら佳いものをと思っても、思うようになるかならないか自分にさえ予言のできかねるのが述作の常であるから、今度こそは長い間休んだ埋合わせをするつもりであると公言する勇気が出ない。そこに一種の苦痛が潜んでいるのである。
このような緒言からはじまる、夏目漱石の「彼岸過迄」を読んだ。
著者は夏目漱石が書いた「こころ」がありとあらゆる本のなかで一番好きだ。高校生の頃にはまるで推し活のように同じ本を何冊も所持していたものだし、授業で学ぶ時期には「なぜ一部しか載っていないのか、これでは良さが伝わらない」と厄介な考えをしていた。
その癖こころが三部作の中の一つであることを知ったのは高校を卒業してからのことで、沢山の本の中に紛れていたのが本書である。4年も積んでいた言い訳はこの際割愛する。
冒頭の文章を初めて読んだ時、素直に「夏目漱石も人間なんだな」と思った。私の中で夏目漱石は「大好きな文豪であり、神格化されているもの」だった。そのため、自分の中で持っている夏目漱石像と少しだけ乖離している部分があり、驚きがあったのだと思う。
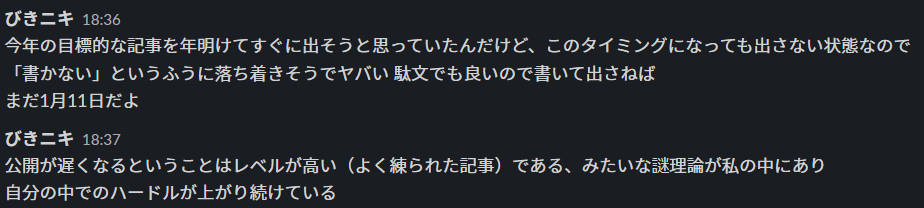
実はこの本を読み始める直前、私も少しだけ同じような意見をボヤいていた。そのためタイムリー過ぎる文章に見事にやられてしまい、緒言だけで長々と感想を垂れている始末である。
本作は一言で云えば「敬太郎という男が、自分の人生において己の行動による結果、経験によって得たものがないのを悩み、数人の人物のエピソードを聞いて、己の人生経験の足しにする話」である。後半では、須永という男と、天真なその従妹との恋愛問題を軸にして、自意識をもてあます内向的な近代知識人の苦悩が描かれている。
人間の仄暗い内面に焦点を当てており、漱石の緻密な心理描写が随所に光っているのが特徴だ。以下は私が好きな部分の抜粋である。
自白すると僕は若い女ことに美くしい若い女に対しては、普通以上に精密な注意を払い得る男なのである。往来を歩いて綺麗な顔と綺麗な着物を見ると、雲間から明らかな日が射した時のように晴やかな心持になる。会にはその所有者になって見たいと云う考えも起る。しかしその顔とその着物がどうはかなく変化し得るかをすぐ予想して、酔いが去って急にぞっとする人のあさましさを覚える。僕をして執念く美くしい人に附纏せないものは、まさにこの酒に棄てられた淋しみの障害に過ぎない。僕はこの気分に乗り移られるたびに、若い時分が突然老人か坊主に変ったのではあるまいかと思って、非常な不愉快に陥いる。が、あるいはそれがために恋の嫉というものを知らずにすます事が出来たかも知れない。(中略)この嫉心が燃え出したのだと思った時、僕はどうしても僕の嫉心を抑えつけなければ自分の人格に対して申し訳がないような気がした。僕は存在の権利を失った嫉心を抱いて、誰にも見えない腹の中で苦悶し始めた。
本書は全六章の短編小説を連ねることで一編の長編が構成されている。各章は時系列も異なれば、文体も違う。幾つかの章では語り手自体が変わることもある。短編小説であるため、背景を理解してきたタイミングで章が終わってしまうこともあった。全体を通じて一貫する物語はなく、消化不良感が残る。
そのため、読書時に高い集中力が続いたかと聞かれると私の答えは否である。殆ど気合いで読み切ったようなものかもしれない。私の読解力が大幅に低下したことを痛感させられた。
改めて全体を通してみると、敬太郎はただ狂言回しの1人にしか過ぎず、実際のところは須永が主人公と言って差し支えないだろう。最後に「結末」という見出しでこのようにも触れられている。
敬太郎の冒険は物語に始まって物語に終った。彼の知ろうとする世の中は最初遠くに見えた。近頃は眼の前に見える。けれども彼はついにその中に這入って、何事も演じ得ない門外漢に似ていた。彼の役割は絶えず受話器を耳にして「世間」を聴く一種の探訪に過ぎなかった。
話の中では、特に「外と内」あるいは「外面と内面」の対比が際立っていたように感じる。
外の世界に関心を向ける者と、自己の世界に籠って想像が止まらない者。他者という"内側で自己が作り上げた偶像"とそこから乖離している本来の人物像。外からの客観的な人間観察から、自己の内面を告白する文体での主観的な自己分析。
「僕は世の中の人間の中であなたを一番信用しているから聞いたのです。あなたはそれを残酷に拒絶した。僕はこれから生涯の敵としてあなたを呪います。」
また、漱石は本書執筆前に「持病の悪化による自身の危篤(修繕寺の大患)」「娘の死」という二つの死を経験している。前者の経験は全体的な構成や雰囲気に、後者の経験は「雨の降る日」という章に色濃く反映されているのではないかと思う。ここでは詳細に触れないので、気になる人は是非読んで欲しい。
好きな文章抜粋
彼は、「田川さん、あなた本当に飲けないんですか、不思議ですね。酒を飲まない癖に冒険を愛するなんて。あらゆる冒険は酒に始まるんです。そうして女に終るんです」と云った。
僕は常に考えている。「純粋な感情ほど美くしいものはない。美くしいものほど強いものはない」と。強いものが恐れないのは当り前である。僕がもし千代子を妻にするとしたら、妻の眼から出る強烈な光に堪たえられないだろう。その光は必ずしも怒りを示すとは限らない。情けの光でも、愛の光でも、もしくは渇仰の光でも同じ事である。僕はきっとその光のために射竦られるにきまっている。それと同程度あるいはより以上の輝くものを、返礼として彼女に与えるには、感情家として僕が余りに貧弱だからである。僕は芳烈な一樽の清酒を貰っても、それを味わい尽くす資格を持たない下戸として、今日まで世間から教育されて来たのである。
その心持は純然たる恐怖でも不安でも不快でもなく、それらよりは遥かに複雑なものに見えた。が、纏って心に現れた状態から云えば、ちょうどおとなしい人が酒のために大胆になって、これなら何でもやれるという満足を感じつつ、同時に酔に打ち勝たれた自分は、品性の上において平生の自分より遥に堕落したのだと気がついて、そうして堕落は酒の影響だからどこへどう避けても人間としてとても逃れる事はできないのだと沈痛に諦めをつけたと同じような変な心持であった。
白状すると僕は高等教育を受けた証拠として、今日まで自分の頭が他より複雑に働くのを自慢にしていた。ところがいつかその働きに疲れていた。何の因果でこうまで事を細かに刻まなければ生きて行かれないのかと考えて情なかった。僕は茶碗を膳の上に置きながら、作の顔を見て尊い感じを起した。「作御前でもいろいろ物を考える事があるかね」「私なんぞ別に何も考えるほどの事がございませんから」「考えないかね。それが好いね。考える事がないのが一番だ」「あっても智慧がございませんから、筋道が立ちません。全く駄目でございます」「仕合せだ」 僕は思わずこう云って作を驚かした。