このぼやけた悲しみや諦めがはじまったのはいつからだろうと振り返ると、やはり立ち止まるのは12歳の頃だった。まだ生まれた街で暮らしていて、中学受験を終えた頃だった。長い間病気で入院していた父がとっくのとうに亡くなっていたのを母から聞かされた。それからよくわからないまま姉や従兄弟たちがいる東京に越してきて、よくわからないまま学生生活も終わりに近づいている。死という状態がよくわからないのだ。しばらく会えていなかった人が死んだと言われても、この目で確かめたわけじゃないし、また会えるのではないかと待ち望んでしまう。今でさえ遠く離れたどこかにいるような気がするのだ。ただひとつ確かなのは、今のわたしを形づくる大きな要素のひとつは父の不在であり、父の不在によってわたしは自分の孤独の存在に気づいたということだった。父がいたら東京には来なかったかもしれないのに、この街を一緒に歩きたかったな、都会で働く今のわたしをどう思うかななどと考える。その度に悲しくなるのは、幼いわたしにとっての父は多少思い出せても、ひとりの人間としての彼についてわかることがほとんど何も無いからだった。そこに生死は関係なく、いくら家族でも自分以外の人間のことは完全にはわからない、それがわたしの孤独のもとなのである。そして今、この短い生の第1章が終わった(前回書いたように)証として、家族という最初に出会う他者について、そこからはじまった孤独について、かたちにしようと決めた。
それが卒業制作『Our strangers』になった。タイトルは、いちばん身近なはずの家族、familyこそがstranger、見知らぬ人、他者なのではないかという意味を込めた。Ourとは、今回は親しい人たちと家族について語ったその声がメインとなるので、わたしだけでなく「わたしたち(それぞれ)の見知らぬ人」を指している。それぞれ長く時間を分けてきた3人とできるだけ普段通り話し、旅先で川を見ながら、夜道を歩きながら、インターネット越しに録音した。そして最後に母とも眠る前に話をした。みんなごく個人的な経験を話してくれて、家族という関係性の多様さや厄介さを改めて感じた。特別な時間だった。まだゼミの先生にしか全編は見せていないけれど、メールでいただいた感想が、こんなにも意図が伝わるのかと驚きつつうれしかったのでそのまま載せる。信頼できる大人が先生として存在していてうれしい。
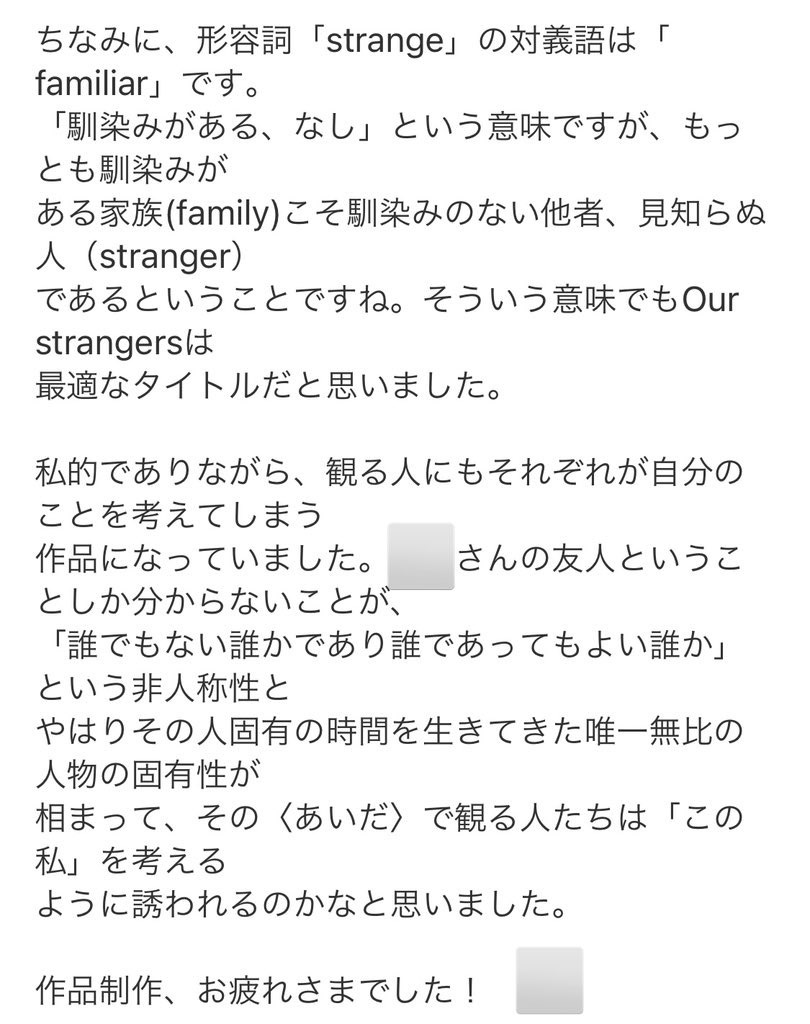
また、映像については、以前つくったシネエッセイ(これも公開するか考え中)からもう少し広がって、これまでに撮りためたさまざまな風景を日記のように繋げた。音声とはほぼ関係がなく、ただわたしがスマホで撮ったいつかの世界たち。影響を受けたのは詩人で映像作家のジョナス・メカスである。リトアニア出身の彼は第二次世界大戦末期に難民として逃げたニューヨークでカメラを手にし、日記映画というジャンルを生み出した。彼は家族や友人、日常風景をひたすらに映す。あるとき、つかれきった身体を引きずって映画館に入り、自分とは何にも関係がないはずのそれらをただ眺めながらなぜかほろほろと心が解れるのを感じた。おそらく、撮影する彼のまなざしにわたしは癒されていたのだと思う。特に母や娘など家族を映しては、時々カメラ越しに話しかける声はとてもあたたかかった。そのまなざしを受け継ぎたい、わたしもただ目の前の現実を平等に記録したいと思った。以下は制作論文にも引用したメカスの言葉。
「この時期、わたしは実際に存在する現実に執着していて、どう撮影しようと、それ自体で独立しうる珍しい出来事には、興味をもちませんでした。平常と異なることには、どうしても興味がわかないのです。おもしろく思えたのは、ありきたりな日々の出来事、街頭の情景や、空から降る雪、風になびく木々をどう捉えるか、ということです。そうした事柄をどのようにスクリーンに映し出せば、わたし自身にとって、わたし以外にもそれに目を向ける人にとって興味あるものとなるか、そこを知りたい。それがわたしの主な関心事でした。」(『ジョナス・メカス―ノート、対話、映画』より)
これはまさに今のわたしの主な関心事でもあった。彼の映画を観ていると、このような彼のまなざしがわたしのまなざしに変わる瞬間があった。見知らぬ景色が、わたしが見たあの揺れる木や流れる水、車窓からの夕日になるのだった。映画を観ているはずのに、いつのまにか記憶を辿っているその時間がたまらなく癒しになった。おそらくいちばん知られている彼の作品に『リトアニアへの旅の追憶』がある。彼は常に「現実」を映すことにこだわるけれど、映像による日記である限り、それは同時に現実が再構成された「虚構」でもある。今回わたしも同じように、時系列もばらばらに、かつ会話を重ねることで撮影したときとは異なる見方ができる「虚構」を作り出した。記憶は時間が経つほどに良くも悪くも事実から変化し、思い出したときの心身の状態によってさまざまに感じる。日記たちを編集しているとき、これはわたしの追憶と虚構であって、現実そのものではないことに少し安心したようにも思う。つまり、『Our strangers』はシネエッセイでも日記映画でもある。ただ、重要なのはわたしだけの生の記録ではなく、話をしてくれた彼女たちの唯一無二の生の記録でもあるということ。それぞれとの会話の終わりに、顔があまりわからないように少しだけ彼女たちを撮らせてもらった。カメラを向けることの暴力性は理解しているつもりだが、今生きているその姿を記録したいと思ってお願いした。また、最後には自分の姿もわかるようにした。わたしも今ここで生きているから。
これを観てくれた誰かが自分自身や家族、生そのものについて考えるきっかけになればうれしい。いつか大きいスクリーンで見てみたいとも思うけど、きっとひとりでいるときがいちばん似合う映画と思う。眠る前や散歩の途中、帰りの電車など。
二度と映画をつくらないつもりでつくったけど、終わってしまうともっといろんな人と家族の話をしたくなった。続きをつくるかもしれない。生きていればまたつくるかもしれない。
12/20追記 彼女たちに許可をもらって、限定ではなく一般公開することにしました。この映画を観ているときだけでも、あなたがあなた自身をただ見つめられるように遠くから祈っています。よかったら観てください。
https://www.youtube.com/watch?v=ihCfWo9FVd0&t=1s&pp=2AEBkAIB