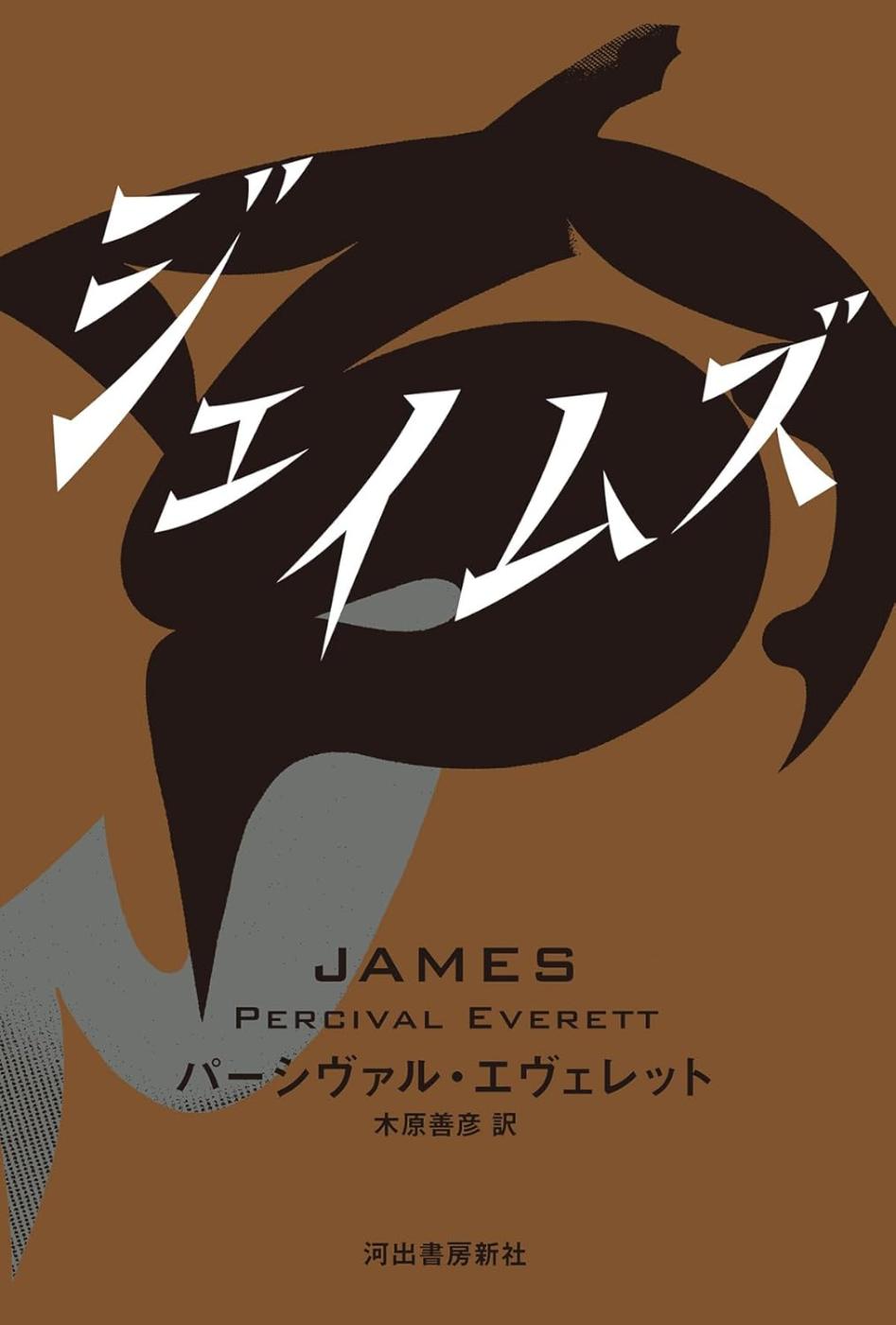これは奴隷ジムの物語だ。『ハックルベリー・フィンの冒険』のヴァリアント(異説)でもある。なにより、奴隷制を語ったお話であり、生き延びをテーマにしたお話であり、注意深くアナクロニズムを配した、読者をニヤリとさせるエンターテイメントでもある。
時代は南北戦争開戦期に設定されている。それがわかるのは中盤のことだ。しかし政治の話はいっさい出てこない。政治家も高級軍人も出てこない。兵隊の様子も仔細には描かれない。戦争のシーンはなく、北軍と南軍が放つライフルやマスケット銃の音も大砲の音も聞こえない。この小説のなかでは、黒人に向け、奴隷の持ち主である白人が撃つ。
ジムは白人から本を盗む。しかし「黒人の書いた実話」というテイの本をすぐに放り出してしまう。夢のなかでヴォルテールやジョン・ロックと対等に会話し、辛辣な物言いで論駁する。
彼は近代人というより現代の知識人に近いメンタリティを持っている。文学部の学生が過去にタイムスリップしたかのようだ。批判的なものの見方で周囲の世界を観察している。そして、戦争に対してはほとんど関心を向けない。彼は、この戦争が仮に「奴隷制」をなくすことになったとしても、別のかたちの差別に置き換わるだけだろうと考えている。
この小説における最大のアナクロニズムは、『ハックルベリー・フィンの冒険』と時代設定が違うことではない。ジムの批判精神がアナクロニズムの中心だ。これが良い意味で読者の違和感をかきたて、物語を駆動させていく。彼が、世界史に残るような思想家たちより、はるかにこの世界の残酷さをよく理解している。
これはひとりの奴隷の意志の物語だ。彼は逃亡し、妻と娘を迎えに行こうとする。これは最初からなにも変わらない。しかし同時に、ひとの意志をしつこく阻む自然の物語だ。無力な男をふりまわすミシシッピ川の話だ。
文学に現れる川というものは、まず第一義的に「渡るもの」だ。あるいは渡れずに「引き返すもの」だ。英雄は川を渡る(カエサルはルビコン川を渡った)。英雄になり損ねる男は川を引き返す(ネロ・クラウディス・ドルススはアウグストゥスの命を受けゲルマニアの蛮族を駆逐したが、エルベ川を引き返し、ローマへの帰り道に落馬して死ぬ)。好きな異性に会うために星の大河を渡る者もいる(牽牛と織姫)。川を渡るともはや後戻りのできない過酷な運命を歩むことになる(『ニーベルンゲンの歌』のライン川)。まったくの異界、人知の及ばぬ別世界が開けることもある(小松左京『ゴルディアスの結び目』)。川はひとの意志を試す。
しかしこの小説のミシシッピ川は、けっしてジムたちを対岸へ渡らせようとしない。対岸に近づけるというきざしがまったくない。たしかに結末は、彼は北へ向かっている。川を渡っているのかもしれないが、渡河のシーンはない。小説のなかのミシシッピ川はほとんどのシーンで執拗にジムたちを阻み、ジムたちは川を下ったり上ったりをただ繰り返し、そのなかで味方や敵と出会い、盗み、別れてはまた出会い、同胞の少女は殺され、川辺に埋葬する(埋葬したところで、川の流れが土砂をえぐり、死体を押し流してしまうことをジムは知っている。文学に現れる川の表象のもうひとつのパターンは、「川を下って海へ向かう」、つまり「新天地へ向かう」というものだ。しかしミシシッピは南へ流れる川だ。黒人のための新天地などなく、そこは死者の世界でしかないということをこのシーンは象徴している)。
濁流に呑まれ、生かされ、食べ物を得て、眠り、他者と出会い、生き延びては死にかける。オデュッセウスのようだ。
そう、この物語は『オデュッセイア』のパロディでもあるのだ。帰還したオデュッセウスは、妻を奪おうとする男たちを皆殺しにして、妻と息子と(彼は父と一緒に殺戮に参加するけれど)館を取り戻す。ジムも同じだ。「繁殖工場」から妻と娘を救い出し復讐を果たす。
考えてみるとオデュッセウスとジムはよく似ている。両方とも巧妙な駆け引きと先回りで難局をその都度切り抜ける。他者の反応をよく予測して動く。限られた選択肢のなかで最良の行動を為そうと努力する。サバイバルのチートでもあって、そもそも両者ともゼロから筏を作れるし、ジムはナマズを釣っては干物にし、薬草の知識も豊富でケガの処置も適切に行う。
オデュッセウスは変装と嘘の名人だ。王族でありながら平然と乞食の恰好をするし(楽しそうですらある)、大事なことは器用な嘘ではぐらかす。ジムは黒人なのに「黒人奴隷を演じる白人」を演じる羽目になる(オデュッセウスのように自信満々で演技することはできないにしても)。そして最後には、ハックに「嘘つき!」と非難されることになる。
オデュッセウスは「誰にでもなれる人間」だ。ジムも同じだ。だから最後に彼は「ただのジェイムズ」と名乗るのだ。
オデュッセウスを翻弄したのはオリュンポスの神々だったが、ジムを翻弄したのは奴隷制という人間が生み出したシステム、関わる全ての人間の人間性をすりつぶすミンチマシーンだった。奴隷制は、キリスト教の司牧システムから牧者の任務(牧者は羊たちの奉仕者でなくてはならないという掟)をはぎとって、商品経済と結合して生まれた。ジムは「インチキなドミニコ修道士」とラス・カサスを蛇蝎のごとく嫌っているが、それはこの修道士が司牧システムから奴隷制を生み出す理路を準備したひとりだったからだ。
彼は現代人のような俯瞰した視点を持てているのに、あるいはそれゆえに、半ば諦観のようなものが染みついてしまっている。このシステムの根深さ、巨大さ、人間という生き物の本性と結びついているシステムを思うと足がすくむ。だが、彼は子どもを虐待し、同胞をレイプする白人を目の当たりにしてついに激怒する。オデュッセウスのように。オデュッセウスは冷静に頭を動かしながら、同時に憤怒に身をまかせ、敵を殺戮する。ジムも同じだ。彼は幻想のなかでジョン・ロックを正当なロジックでなじりつくし、銃を手にする。
私は彼の前に立った。
「誰だ貴様?」と彼は訊いた。そして銃を私に向けた。
私は拳銃を彼に向けた。「私は死の天使。甘き正義を果たすために来た」と私は言った。「私は神のしるし。おまえの未来だ。名前はジェイムズ」。私は拳銃の撃鉄を起こした。
「たわけたことを」。彼も撃鉄を起こした。
私が放った銃弾の音は大砲のように谷に響いた。その反響は永遠に続くように思えた。私と一緒にいた者たちは立ち止まり、男が鉛の弾を受けるのを見た。寝間着を着た男の胸は赤く破裂した。彼の倒れ方は木が倒れるときとは似ていなかった。大きさを感じさせるところはどこにもなかった。彼はただ倒れた。うつ伏せに。私たちの誰にも見えない闇の中に。男の背後にいた女たちが悲鳴を上げたが、その声は炎の轟音と闇に掻き消された。風が強くなり、炎を大きく燃え上がらせた。
まるで西部劇のようではないか。黒人が白人のガンマンのように銃を手にする。クリント・イーストウッド扮する放浪のガンマンのように、白人を打ち倒す。ジムは誰にでもなれるのだ、オデュッセウスのように。ジムは、ついに白人の十八番なエンターテイメント「西部劇」を盗む。ミンストレルショーの意趣返しだ。
(アナクロニズムがここにも混入するが)マーク・トウェインは事業に失敗し、妻を亡くし、子を亡くし、老境に入るにつれ虚無主義的な運命論者、悲観論者へと変わっていった。だからと言ってその作品は、いまだに続くこの不愉快な現実を(いろいろ文句は言われつつも)「なじる」ことをやめない。諦観に沈むこととなじり続けることは(奇妙に思えるかもしれないが)両立できるのではないか。文学に携わる者は書くことをやめてはいけない。翻訳をやめてはいけない。わたしたちは読むことをやめてはいけない。誰かが、この世界を、あるいはわたしをなじる言葉を受け止めることが生きることだ。この物語が閉じたあと、ジムがどう生きたか書かれていない。けれど、銃ではなくちびた鉛筆で自分について書き、そうすることで、死ぬまでなじり続けたと思いたい。
さて、ハックである。
ハックが自分の息子であるとジムは告白する。これはどういうことなのか。どういう意味を持っているのか。もちろんトウェインの原作にはこのような設定はない。トウェインがぜったいに思いつかない設定だろう。この告白は、ジムがの「黒人であること」の苦しみと桎梏を、ハックに与えたことにならないか。ハックが自由であり続けるためには、知らせないことが最善なのではないか?
しかしジムは、自由を得るためにはオデュッセウスのようでなければならないことを知っている。オデュッセウスは変装と嘘の名人だった。限られた選択肢のなかで最良の行動を為そうと努力する人間だった。ジムもそうしてきた。「パス」をしている同胞もいることをジムは知った。そういう生き方もある。生き延びがもっとも重要な世界において良し悪しの問題ではない。ただそれを続けることができるかは別問題だ。
ハックはジムを「嘘つき」と言う。ハックはジムの告白を信じない。オデュッセウスの言葉には裏があるものだ。ジムはそれがわかっているからハックに告白したのだ。ほんとうにジムは聡い人間だ。ハックが告白を嘘だと考えたか、事実だと受け取ったかはわからない。たぶんハック自身にも自分がいまどう思っているのかわかっていない。ジムは自身の告白が嘘であれ本当であれ同じことだと言う。なぜだろうか。この嘘と事実が見分けられないあいまいさ、苦いあいまいさのなかで人間は自由を得ることもあるかもしれない、ジムはそう考えていたのではないか。
ドゥルーズ=ガタリは『千のプラトー』でこう書いた。
生成変化の主体はつねに「人間(=男性)」〔homme〕だと言える。ただし「人間」がそのような主体となるのは,何らかのマイノリティ性への生成変化に入り、自らのメジャーな同一性から引き剥がされる限りにおいてのことだ。
「人間」とは、男性であり白人であるということ。アメリカの奴隷制とはまさにこのような「人間」のシステムが、あけすけかつ暴力にまみれてたちあらわれたものだ。どのように「人間」に対抗するのか。生成変化によって、とドゥルーズ=ガタリは説く。自身のマイノリティ性だけが生成変化を起動させる。黒人自身が黒人になるという生成変化だってあり得る。そのときつねに別のマイノリティとの間になんらかの同盟だって生まれうる。
アクティヴな媒体となるためには、マイノリティもまた、マジョリティとの関係において規定される集合であることをやめなければならない。
黒人が黒人へ生成変化すること、女性が女性へ生成変化すること、自身のマイノリティ性を認め、「選択」して、運動/闘争を(どのようなレベルであろうと)はじめること。これはきっと「パス」とは違う道だろう。たぶんジムは、この自覚をミシシッピ川のほとりで得たのではないか。息子(のように想っている)ハックに知らせたかったのは、これじゃないかと思ったりする。
ジムは息子ハックの魂に種子を埋めた。自由のために選択する機会が、ハックにもいつか来るかもしれない。たぶん、来るだろう。種が芽吹くように、彼は祈りながら告白したのだと思う。
この物語のハックは、気づけただろうか。気づけてたらいいな。