
松任谷由実という怪傑について語るとき、わたしは「春よ、来い」の歌い出しから語り始めることにしている。
「春よ、来い」のイントロを脳内で流す。すると、それだけで桜の舞うような、木々の隙間に煌めきがまどろむような、徹底的にうつくしい風景が瞼に浮かぶ。それは人々が春を歩む足音にも聞こえるし、いっぽうで思い出したように降る驟雪のようでもある。
そのフレーズは2度訪れ、遠くに聞こえていたはずの春がゆっくりと色めいていく。人それぞれが持つ冬の終わりの価値観があり、春の予感が待っている。
そして、松任谷由実の声がする。歌い出しだ。
淡き、光立つ俄雨。
あわき、光だつ、にわか雨。初めてこの歌詞に出会った時の感動は忘れられない。誰がどうして、「春の歌を書いてください」と言われて「淡き、光立つ俄雨」と書き出すことができるだろう?
調べのうつくしさだけではない。レンズの遠近も、切り取り方も、言葉の重さも、すべてが完璧にイントロの風景を受け継いでいる。こんな完成されたうつくしい出だしは他にない。たったこれだけで松任谷由実がいかに希代の天才なのかが分かる。
𓈒𓏸
個人的に愛してやまないのは、「海を見ていた午後」という荒井由実時代の曲である。
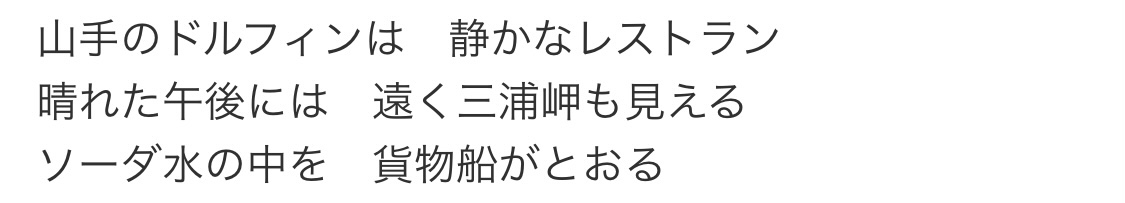
この曲もまた遠近感が素晴らしい。遠くの岬と、近くのソーダ水。潮騒にまぎれて小さく貨物船の音が聞こえるのだろう。レストランが静かだから、嫌でもそのことがわかるのだ。
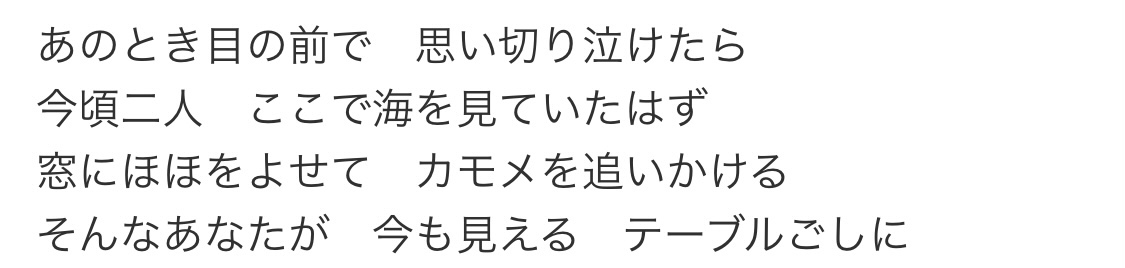
そんな!と思うだろう。そう、これは終わってしまった恋の歌なのだ。やはりわれわれ凡人はは「失恋ソングを書いてください」と言われて、山手のレストランから見える貨物船について書くことはできない。松任谷由実は終わってしまった恋をソーダ水に浮かべることができるのだ。その感性はやはり天才と呼ばざるを得ない。
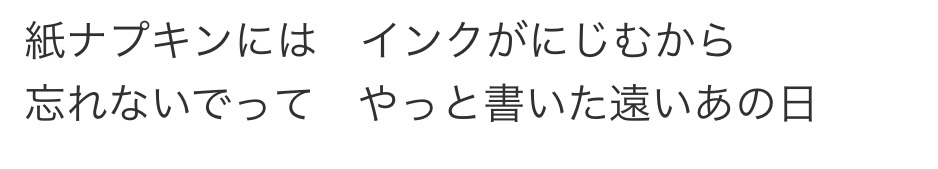
そして、このエピローグである。
紙ナプキンには、インクがにじむから。
この歌はずっと水辺にある。ドルフィン、岬、ソーダ水、海、そしてインク。すべてがにじんでいて、それはどうしてかというと、終わってしまった恋に涙しているからなのだ。あなたを失って悲しい、というたったそれだけのことが、こんなにうつくしく並べたてられることがあるだろうか?
𓈒𓏸
こちらも荒井由実名義だが、「雨の街を」という名曲も紹介したい。
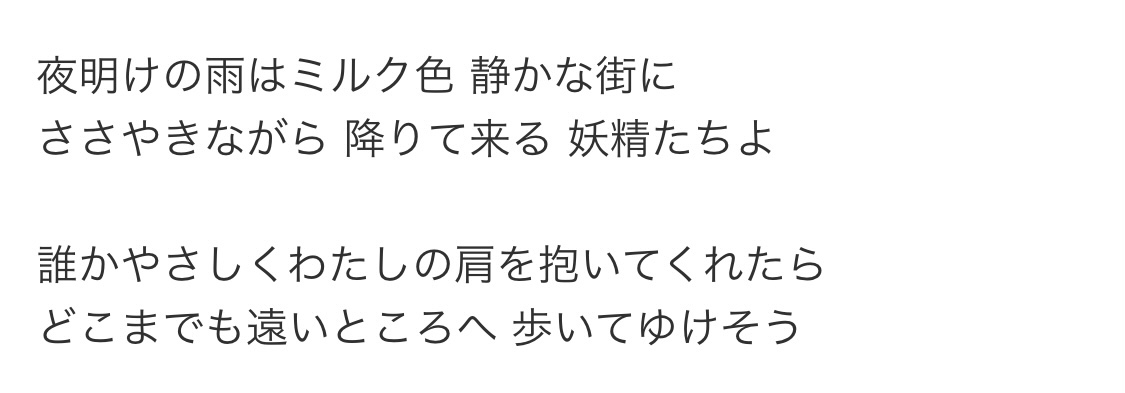
好きだ。たまらない。
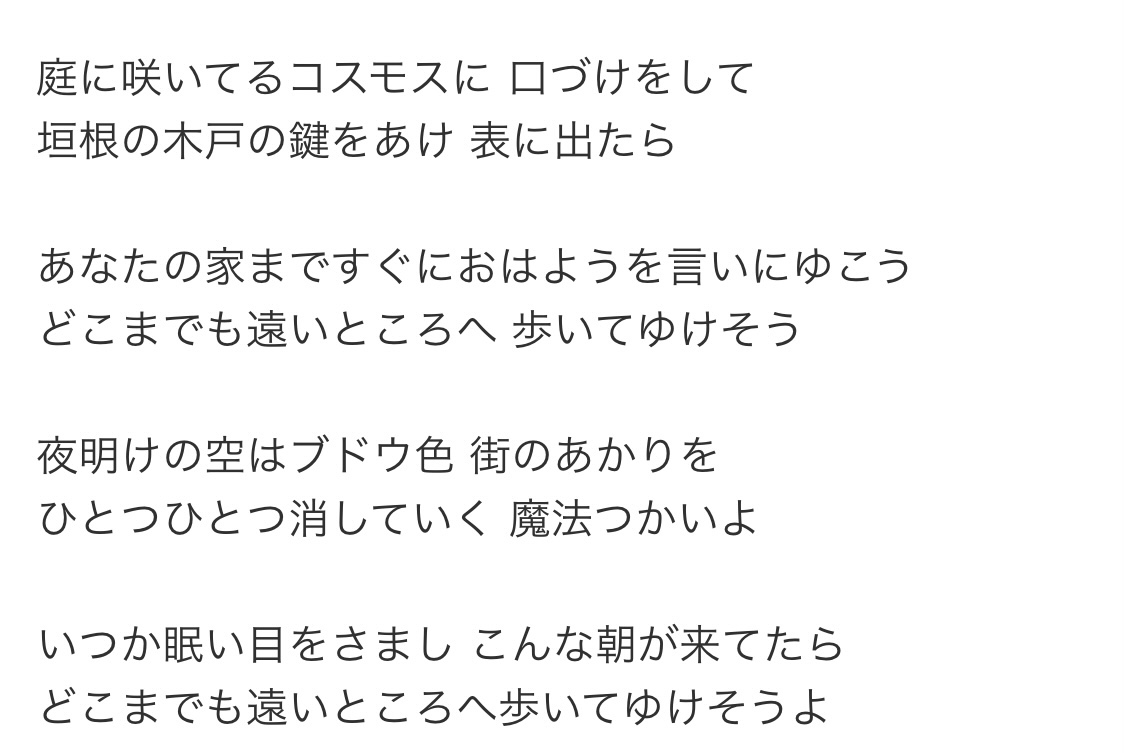
松任谷由実の歌詞を見ていると、言葉など死んでしまえばいいのに、と思う。あまりにも自分の言葉が無力すぎてそう思ってしまうのだ。この曲もそう。文字にするのも無粋で悔しいが、夜明けの街に妖精が降りたつのも、魔法使いがひとつずつ灯りを消していくのも、そのたおやかで柔らかい風景のすべてが、ただあのひとを愛しているという「祈り」なのだ。どうしようもなく、言葉になんてしなくても、これが愛についての歌なのだということはひしひしと伝わってくる。だからユーミンはすごいのだ。
(2024.04.24につづく)