
パニグレ新章「クレイドルパレード」、これ一本で映画ができるSFサスペンスでした。
非常に衝撃的な内容で、自分の考えを整理をしたくて書いていたら、小論文並みの字数になりました。新章に狂わされた同志の皆様、よかったらお付き合いください。
0. はじめに
本記事は、ゲーム「パニシング:グレイレイヴン」26章「クレイドルパレード」の重大なネタバレを含みます。
筆者個人の見解に基づく考察です。これが唯一の解釈ではありません。
1. 哲学的テーマ:「わたしとは何か」

本章を構成するいくつかのテーマがあった。ラミア視点では過去との心理的な訣別と克己の物語だったし、複製体ノアンやフォン・ネガットサイドの思惑も絡む群像劇的な見方もできる。
ただ、その中でもとりわけ衝撃的だったのは指揮官視点の物語だろうということで、今回はここを掘り下げたい。
冒頭で惑砂がトロッコ問題を持ち出したから、誰を犠牲にするべきかの倫理的ジレンマの話と混同しそうになるが、本質的な問題はそこではない。
本章の核となる哲学的テーマは「わたしとは何か」であった。すなわち同一性やアイデンティティにまつわる問題である。
物質的に同じ身体を持ってさえいれば、それは指揮官といえるのか?
違う、ならば記憶も持っていたなら?
不完全な記憶しか持たないクローンはオリジナルと同一とは言えないかもしれない。でもそれが完全な記憶を持ち、オリジナルの指揮官と同じ思考をするクローンだったらどうか。
もはや主観的にも客観的にも本物と見分けがつかない存在。それはオリジナルと同一人物と言えるのだろうか。
スワンプマン(沼男)という思考実験がある。
ある男が不運にも雷に打たれて命を落とした。するとどういうわけか、足元にあった沼が雷で化学反応を起こし、その男と分子レベルで全く同じ物質的性質と記憶を持った存在 ー スワンプマン(沼男)が生まれ出てきた。スワンプマンは何事もなかったかのように男の家へ帰宅する。
完全に男と同じ身体的特徴と記憶を持ったスワンプマンの日常生活に全く支障はないし、周囲の人間も入れ替わりには気づかない。本人ですら、落雷から幸運にも生き延びたと自覚している。
さて、スワンプマンは雷に打たれた男と同一人物と言えるだろうか。
今回、指揮官が置かれた状況はこの思考実験とかなり近い。
2. 本章のインスパイア元になっていそうな作品
2-1. 映画『オブリビオン』(2013)
類似のテーマ性を持った物語に、映画『オブリビオン』(2013)がある。人類撤退後の荒廃した地球で単独任務につく男が、とあるきっかけで自身のクローン疑惑に至って奔走する話。
主な共通点は①ポストアポカリプスな世界観でのクローンものであることと、②人間社会と隔絶された閉鎖環境で、③主人公が他者の作為によって「自己の同一性」を脅かされる、という状況。
後述の『月に囚われた男』と合わせて、本章における指揮官サイドの物語のインスパイア元となっている可能性がある。
2-2. 映画『月に囚われた男』(2009)
前述の『オブリビオン』がオマージュを捧げたのが、映画『月に囚われた男』。元ネタの元ネタ的ポジションといえるかもしれない。
2-3. 映画『パイレーツ・オブ・カリビアン - デッドマンズ・チェスト』(2006)
海底を舞台とする世界観とクティーラの役どころは、おそらくイギリス伝承の幽霊船、フライング・ダッチマン号がモデルになっている。特に映画『パイレーツ・オブ・カリビアン - デッドマンズ・チェスト』に出てくる同名船に共通点が多く、参考にしている可能性がある。
フライング・ダッチマン号は、海で死んだ魂を死後の世界へ運ぶ聖なる仕事が課せられていた船だった。映画の描写では、普段は海中を潜航していて突如として海面に現れる姿が見られる。これは、指揮官失踪事件から1年後、多くの死者を乗せて浮上したクティーラの姿と重なる描写である。
また、フライング・ダッチマン号では呪われた乗組員が船の一部になって船長の状態に影響されるようになるのに対して、本章では巨木と一体化したクティーラに同化する点も類似している。

さらに「ポセイドンの槍」をモチーフとするラミアの星6武器「メーティス」も『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズでの描写の影響を受けていると思われる。「ポセイドンの槍」は水中墓にある海の神ポセイドン伝説の槍であり、雷や海の生き物を操る不思議な力を持つとされる。
3. オリジナルの定義、あるいは不確実な自己認識
話を「クレイドルパレード」に戻そう。
本章エピローグでは、空中庭園は「より完全な記憶を持った個体」をオリジナル指揮官として認定したことが描かれている。
しかし、空中庭園に戻った指揮官本人は自身を疑い続けていた。身体と記憶に不自然な点がないからといって、自己の同一性が担保されるとは限らないと考えているのだろう。それは至極もっともな指摘である。
実際、ヒポクラテスから「あなたが本物」の客観的なお墨付きを得たかに見えたが、最後の不穏な引きで検査結果の信頼性が揺らぐ。本章エンドの段階で、指揮官自身は「自分が絶対にオリジナルである」との確証を得られていない。
指揮官自身が「私が私である」ことを証明できていないのである。
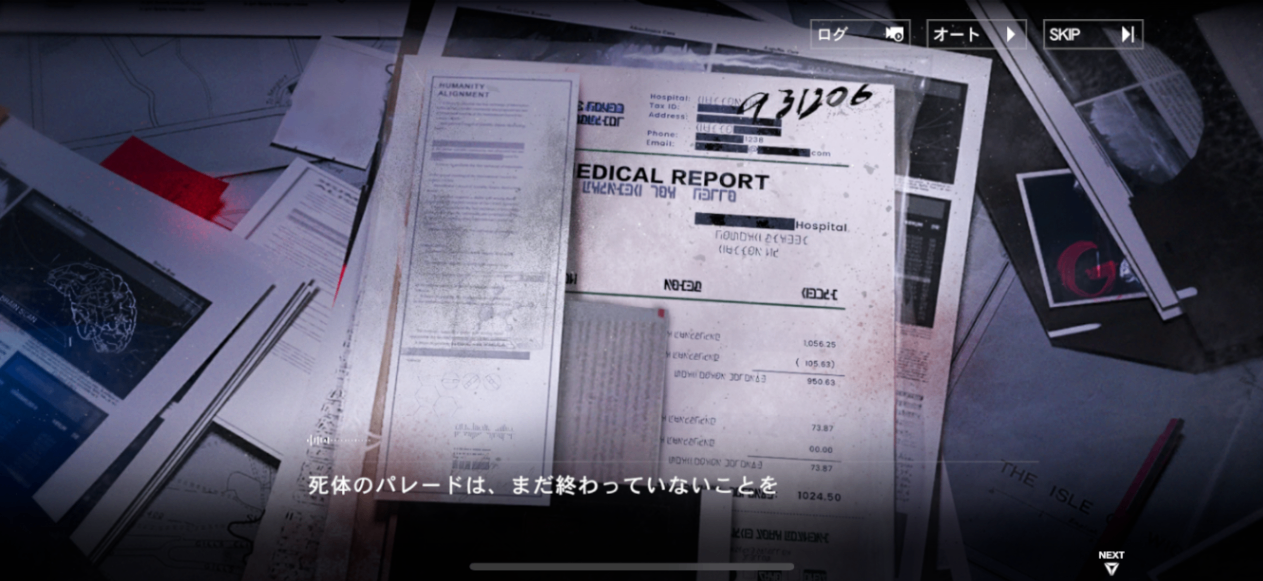
自己の存在の証明に関する議論は、哲学の領域において古くから活発に行われてきた。デカルトは、方法的懐疑から導かれる「我思う、ゆえに我在り」を踏まえて 「わたし」の精神(意識)が最も明証的に認識できるものは精神それ自体であると主張した。
これを批判する立場であったスピノザは、デカルトの「我思う、 ゆえに我在り」の命題に対して「我」と「思う」を分離する解釈をし「我思う」 と考えているものが本当に「我」なのかわからないという批判を加えた。
カントは、認識論の視点から、デカルトのいう「我思う」は多くの思惟を統覚する概念であり、実体と解釈するべきでないとした。
「わたし」の存在を「わたし」自身が明証的に示すことは難しく、このように現実の世界でも様々な哲学的立場で語られてきた問題でもある。
4. 良質な地獄を見せ続けるパニグレ
何を以て本物の指揮官と判断するか。
何を以て私が私であることを証明するか。
複数の個体から、どれを「オリジナル」として自他が認めるか。
何を基準に個人のアイデンティティを規定するのか。
あるいは逆の立場として、クローンとして生み出された者は、本人にクローンだという自覚がなく生きていたとしても「偽物」として粗雑に扱われ、救われない運命を強いられるものなのか。果たしてそれは是とされるべきことなのか。
同一性、自己認識、アイデンティティ。
そういった哲学的・倫理的にも人それぞれ見解の分かれるテーマは、これまで構造体サイドで描かれてきた。特に九龍環城でのルシアの鴉羽換装は印象深い。
それがここへ来て人間サイド、それも一人称視点という叙述トリック的方法で「他人事ではないぞ」と再提示してきた。
これを読んでいるあなた自身も、クローンではない本物のあなたであることを証明できるだろうか?そんなメタな問いも聞こえてきそうな鋭い切り口が、パニグレの良質な地獄たる所以(褒め言葉)である。
余談だが、本章と同じようなテーマを別の切り口で取り扱ったゲームタイトルがもう1本思い浮かんでいて、合わせて語りたいところなのだが、重大なネタバレにつながるため泣く泣くここでの言及は控えておく。
※ それでも知りたい方には、聞いてくれれば答えます。
5. 本章の個人的な所感

最後に、これまで述べてきた考察を踏まえた感想を。
映画はもちろん、こういった哲学的テーマを主題に据える試みはこれまで他のゲームでもあったはず。おそらくSFサスペンスの領域では、手を変え品を変えてやり尽くされてきたパターンなのだと思う。
ただ、なんといっても魅せ方が美しかった。
本章で主に描かれたのは、とあるクローン指揮官(?)が体験した海底のブラックボックス内での出来事である。誰も知らない、指揮官本人ですら知らない、指揮官最期の大仕事。ラミアがその唯一の見届け人となった。
ラミアと過ごした指揮官がオリジナルと同一の存在であるかはさて置き、それがクローンだとしてもあの場にいたのは確かに指揮官の人格を持った指揮官で、指揮官が指揮官としての判断で、残り少ない命を賭して為したことが、生きる者に希望を繋ぐために最期まで戦うことだった。オリジナル指揮官とほぼ同じ記憶を持ち、同じ思考をするクローン指揮官(?)の、泥臭くも誠実で気高い生き様。

シナリオとしても、昇格者という、空中庭園と大っぴらな協力関係を結べないながらプレイアブルとして実装されるポジションのラミアをどう扱うかというメタ的な問題があって、そこの解決策も期待していた。
結果、クローズドな環境に閉じ込めて互恵関係を結ぶところまでは予想通りといった印象だったが、ラミアを唯一の観測者として、死にゆく指揮官の意思を生きる者に繋ぐ存在にするという落とし所は脱帽だった。
また「ソシャゲの主人公(=指揮官 ≒プレイヤー)が退場するわけない」という先入観を逆手に取り、オリジナル(とされている)指揮官の描写を終盤まで秘匿したことが意外性を生んだ。一応の安心を得たかに思えた最後の最後に疑心暗鬼を煽られる、何とも言い難い後味まで含めて、終始情緒が揺さぶられた。
映像・スチル・音楽などの素材も惜しみなく、質・量共に非常にリッチに仕上がっていることで没入感も高い。今までのストーリーで1位を争うほど深く考えさせられ、印象に残る章となった。
もう映画化してくれ。