背景
今、取り組んでいるのは、ベンチャー企業の入社エントリを見やすく集約したものです。noteでタグを見ると、3000件近くヒットするぐらい、入社エントリを書くのは当たり前になりつつあります。

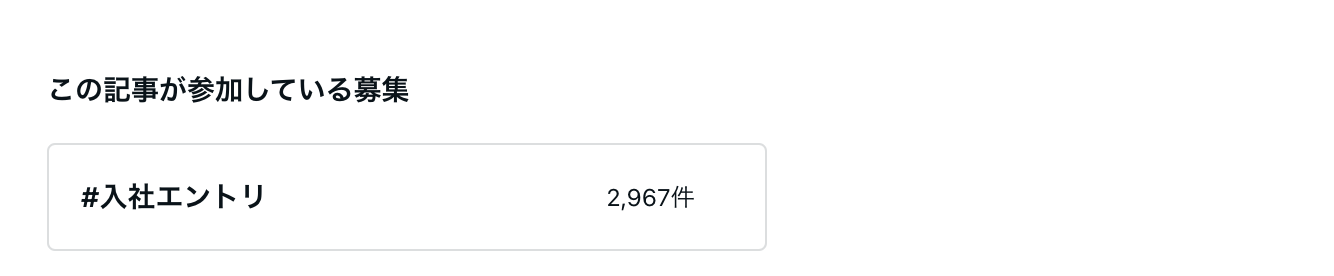
問題点 of 入社エントリ
僕は、既存のものに問題を感じて、その解消をするためにという流れでプロダクトの機能を考えていくことが多いです。
入社エントリの主な問題点
長いので、読める量が限られる
長いので、相当な興味が既にその会社にないと読まれにくい
ブログを全部読んでもらわないと、ブログの中にある情報を知ってもらえない
求職者はその人に興味があるのではなく、会社に興味がる。そのため、1人がどうかよりも会社全体的にどうかを知りたい
30個の入社エントリを読んだとしても、数日で内容は忘れるものなので、長期的には記憶に残りにくい
いくつか書きましたが、特に問題だと考えたのは、長いことです。

Youtubeでも10~30秒のショート動画であれば、見ようとは思う動画でも2時間とかの動画であれば見ようとは思わないはずです。入社エントリの問題も同じです。多少の興味で読むには長すぎるのです。
例えば、メルカリに入りたい人は、メルカリへの入社エントリブログが長くても読む可能性は高いです。ですが、まだ知らない会社であれば、1つのブログを最後まで読んでもらうこと自体が非常に困難になります。
そのため、ショート動画と同様に、1000文字の入社エントリであっても、50文字とかに短くしたものをまず見せることが重要だと考えました。
入社エントリの構成
入社エントリはどの会社も内容は同じで、その人の経歴、会社を知ったきっかけ、転職の軸、入社理由、入社後の感想、今の業務について記載されています。
また、入社エントリの場合、その人の人生やストーリーが見えてくるくらい、詳細な情報が付加情報としてついています。
僕は、そういった付加情報をフィルターのように省けることが大事だと考えました。関心が高まっていない状況では、そういった詳細な付加情報を含んだ長文を見るのはメリットよりもデメリットの方が大きくなると考えたからです。

小分けにすることで、見たいポイントだけ見れるようにするという方針で、今のページをデザインしています。
例えば、どんな人が最近入社しているのかを知りたい場合には、前職だけ見ると、50人いてもサクッとチェックできるはずです。同様に、入社理由を見たい場合には、入社理由だけ見れるようにしています。

同じ項目だけで情報を見ることで、この会社にはどんな経歴の人が入社してきているのかや、どんな入社理由で入社する会社なのかを知ることができるようになります。
参考にしたこと - サッカー移籍情報サイト Transfermarket

サッカーや野球では、選手のレベルやスキルなどが可視化されています。そのため、素人のファンの方でも、各チームにはどんな選手が必要なのかを理解してもらうことができます。
僕は、このスポーツでおきている現象は、小規模なスタートアップでも実現可能ではないかなと考えています。人数もスポーツチームと同じ程度で、スタートアップの会社の多くは社員紹介ページを設けています。
そのため、これらの公開情報や入社エントリの内容を整理するだけでも、求職者自身で自分がその会社に必要なのかやあっているのかがある程度わかるようになるのではないかなと考えています。
期待している効果 - 人が人を呼ぶ
良い会社には良い人材が集まっています。それがもっとわかりやすく端的にわかるようになれば、その情報を元にまた良い人材が良い会社に集まっていくというサイクルが回るのではないかなと考えています。
例えば、今シーズン、山本由伸選手は大谷翔平選手が所属するドジャースに入団しました。ドジャースという球団は元々強豪で魅力的なチームですが、大谷選手がドジャースに入団したことが、山本選手の入団理由の中で大きくなっているはずです。
同様に、小規模なスタートアップでも"誰"が入社してきているのかをもっと見やすくわかりやすく公開することで、同じくらい優秀な人が自然と集まりやすくなるようになると考えています。
もちろん、スタートアップ村の中にいる人は、既に知っていることかもしれないですが、村の外にいるような人にもわかるようにすることが重要だと思います。
退社した人がどこに行っているのか?
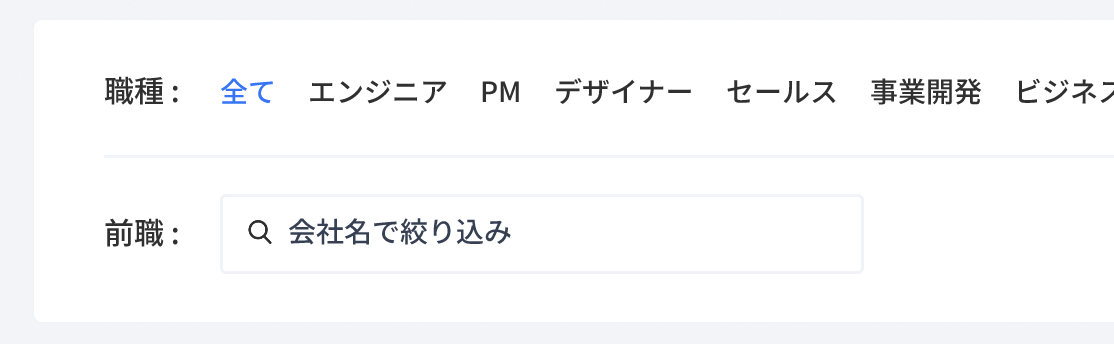
経歴についての情報が集まると、退社した人がどういう会社に行っているのかがわかるようになります。その結果、次にこういうキャリアを歩めそうだなというのを考えながら転職を検討できるので、求職者の不安を解消できるようになると考えています。
700以上の入社エントリを読んで思うこと
① ほとんどの人は自分で会社を見つけて転職していない
現時点で、700名ほどの方の入社エントリを読んでまとめています。一番の驚きはほとんどの人が自分で転職サイトなどで見つけて転職していないことです。推定ですが、5~10%ぐらいの方しか自分で転職サイトなどで検索して見つけたといっていませんでした。
有名なスタートアップであれば、以前から知っていたという人もそこそこいますが、それは非常に限られた会社のみです。
ブログは認知というよりも関心UPに効果がある?
また、スタートアップはnoteなどの発信が定番なので、そういった発信物経由で認知したという転職者が多いのかなと思っていました。
ですが、入社理由や関心を高くした決め手になっているケースはあるものの、認知や関心のきっかけになっているケースは5~10%程度でした。Xで有名な会社の場合、noteで見たことがあるという方は結構いましたが、大抵の会社ではほぼ見かけなかったですね。
非常に多かったのは、
知り合いの社員、経営者がいたなどのリファラル
エージェントの紹介
紹介されたので、何となくカジュアル面談を受けてみた
スカウトで連絡を受けた
仕事を探した始めた段階で連絡を受けた会社の中から選んだ
のように、自分で検索して見つけたというケースではないのが7~8割は占めていたように感じています。
② ベンチャーの転職者の多くは自分で会社を見つけていない
僕は、現時点では、検索性の問題で、ホテル予約サイトのように検索が容易で便利なサービスが広がれば変わるのかなと思っていますが、そうではないかもしれないですね。
この機能を思いついた段階では、会社を知ったきっかけを載せるつもりはなかったのですが、300件ぐらい読んだ段階で、自分の予想と違ってて面白いデータになると思い追加しました。
③ 3000以上のベンチャー企業から1社を選んでるわけではない
大半の人を見ると、スカウトを受けた10社から1社を選んだや知り合いがいたから選んだ、エージェントから紹介を受けたからのように、最初の母数自体が10もないような中から1社を選んでいることが多いことに非常に驚きました。
ホテルの場合、札幌にある300程度のホテルから条件にあった1社を選んでいるという感覚が僕の中にはありますが、転職においては少数派になっているように感じています。
僕はこの問題を解決したいと強く思っています。20-30代の人でホテルを旅行会社の窓口経由で予約するような人はいないはずです。にもかかわらず、転職において、エージェントのようにアナログ?な検索と選定が主流になっているのはどうなのかなと個人的には思っています。
ChatGPTのように、レコメンドというアプローチもありますが、個人的にはフィルタリングだけで3000社程度から10社程度にまでは絞れると思っています。
④ 面接のタイミングで入社を決める人が非常に多い
また、非常に多かったのが面接などであった人たちがみんないい人だったから入社を決めたという入社理由です。そのタイミングでは、軽い気持ちで話すだけという人が、話した印象だけ?で入社を決めたという人の数の多さにも少し驚きましたね。
終わりに
そもそもですが、スタートアップは社員数自体が多くないので、転職の口コミサイトでも口コミがほとんどありません。入社エントリは匿名ではないですが、それでもまとめてみると非常に参考になるものだと感じています。
どんな雰囲気の会社なのかはここだけを見れば大体わかるようにしていきたいですね。