ずっと気になっていて、ようやく読めました。大切にしたい、しなければならないものに出会った感覚があります。まとめることもなく、読後に感じたことを綴ってみよう。語るように。
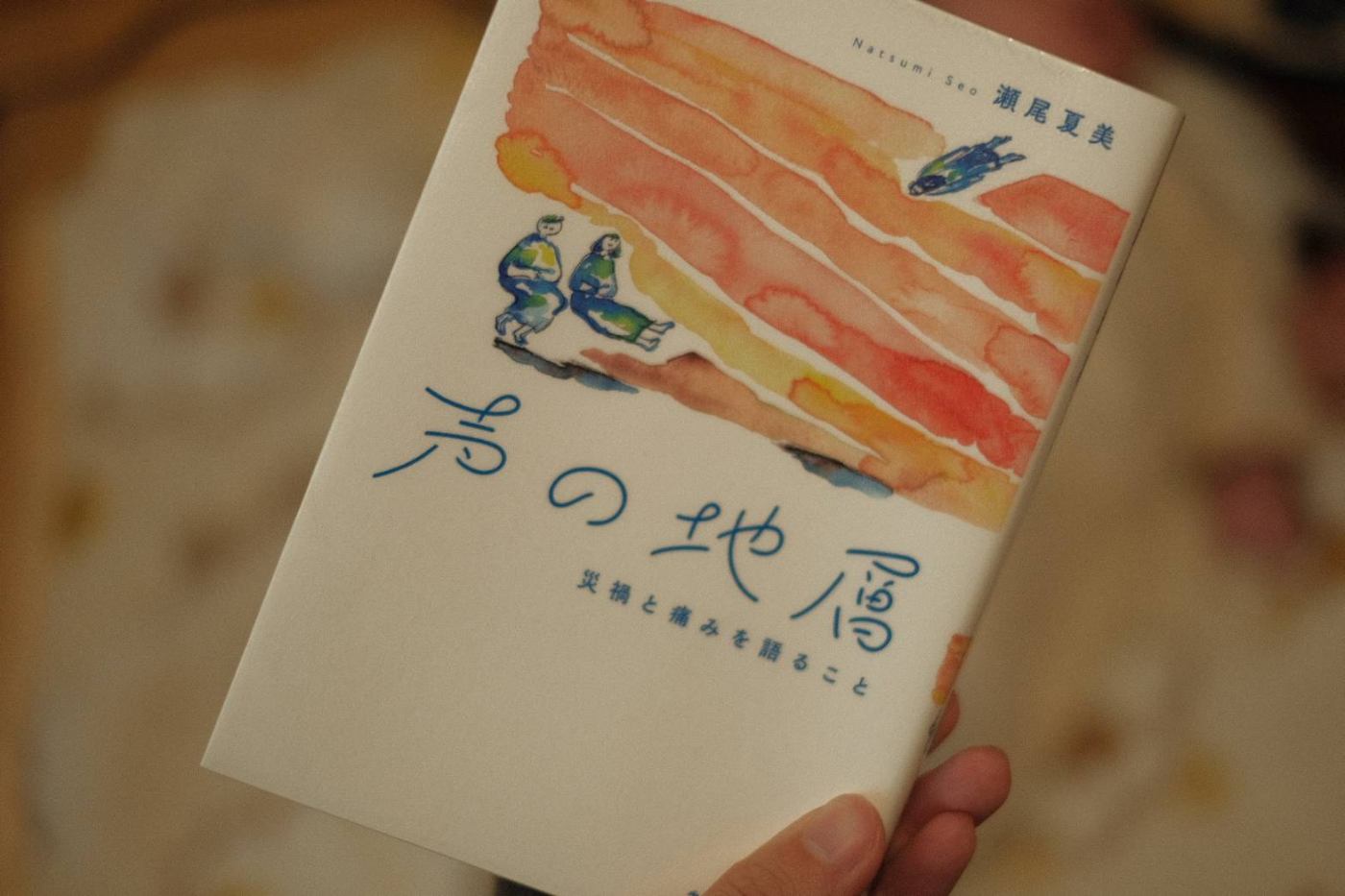
災禍・痛みの語りを聞く活動をしている人の本を読む。
数多の死や痛みを目の前にして、または、記憶にないけれどたしかに足元にして、彼ら彼女らは生きている。
いのちの有限性、世界の脆さ。その儚さを、視界の色が失われるほどにその身に浴びたのに、それでも足や手を動かしている。
この“それでも“は、なんなのだろう。
ふいに、我が子が生まれるまでのことを読み直したくなり、記録用に書いた記事を開く。
あのとき、僕を貫いたものを思い出し、ひとしれず泣く。
そうだった。あの日々で感じたいのちの流れは、僕にも“それでも“をもたらしてくれた。
いつか死ぬのに、なんで生きるんだろう。そう悩み続けていた自分が、「それでも生きていこう」と心から思った、はじめての日々。
仮に、妻が、我が子が、目の前で動かない存在になったなら。僕は、“それでも“を選ぶ自信がない。選べないと思う。
災害や戦争などでは、死の匂いが濃く立ちこめるはずだ。
その現場の報せを見聞きすると、当事者じゃないのに、心が遠くをさまよう。不謹慎かもしれないけれど、それが少し心地よいときがある。
でも、それは匂いが薄まっているからに過ぎない。薄まった死の匂いは、むしろ恍惚を呼び起こす。
じゃあ、濃い死の匂いは?それが目の前に湧いたきたとき、僕はどうなる?
よくよく考えると、災禍のもとじゃなくても、僕のいのちは死によって成り立っている。
何千年ものあいだ、先祖と呼ばれる人の死が積み重なって、その頂上に僕がいる。そして、いつかは僕の上に我が子が立つのだろう。
死や痛みは乗り越えるものなのだろうか。それとも、一緒に生きるものなのだろうか。
濃い死の匂いを身体に取り込んだ存在は、なんで“それでも“と生を選べるのだろう。もちろん、選べなかった存在もいるだろう。そこに優劣はないだろう。
いのち。命ではなく、流れとしての“いのち”。血の繋がりとかではなく、世界にひたすら流れているもの。
「いのちの有限性を抱きしめて、その儚さに打ちひしがれながら、それでも足を進める」の“それでも“にこそ、生が宿るのではないか。
それでも、だけが正しいわけじゃない。だからこそ、その正体を探らないといけない気がする。
なんで、平気な顔をしてそこにある世界を、当たり前のものとして通り過ぎてしまうのだろう。
強烈な匂いに出会わずとも、いのちの有限性は抱きしめられないのか。きっと、どんな日常にも死の匂いはある。死が積み重なった世界なのだから。
死を想えば生が輝く、なんてものではない。輝くのなら、それを掴み取るのなんて簡単だ。
僕は、死を想えば想うほど、生は霞んでいく感覚があった。だから、想わないようにしてきた。
たった数秒で塵のように消え得る存在を、軽んじてしまうのが怖くて。
でも、死を想わない生には、大事ななにかが欠けていて。尊さではなく、もっと宇宙的なもの。自己に還元できないなにか。
いのちは、生と死で成り立つ。いままでの僕の生は、いのちではないのかもしれない。
さまざまな人の語りは、いのちを継いでいく営み。間接的だけれど、この本からその語りを受け継いだ。受け継いでしまった気がする。
いのちの流れを絶やさないため、僕はどう参与できるだろうか。